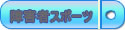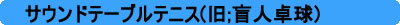

視覚からの情報の代わりに音(聴覚)を利用 した競技です。
台上の球を、ラバーの貼って ないラケットでころがすように打ち合う平面 競技です。
一般の卓球とは異なり、ネットと 台の間は、球が通過できる程のスペースがあ ります。
この競技を誰がいつごろ考案したかは不明で すが、1933年の帝国盲教育研究所で今日 の競技と同じようなルールの「盲人ピンポン 」が公表されています。
「全国障害者スポーツ大会」では、1965年の第一回大会以降 「盲人卓球」という名称で正式種目となって いましたが、2002年に「サウンドテーブ ルテニス(以下:STT)」と改名されまし た。
神奈川県内では「全国障害者スポーツ大会」 の予選を兼ねた「神奈川県障害者スポーツ大 会(STTの部は6月)」のほか、「藤沢市 長杯(10月)」、相模原市「けやき大会( 3月)」などの大会が開催されています。
当 センターでは、競技経験の少ない方でも気軽 に参加できるよう、正式ルールに準拠しつつ も若干のローカルルールを採用した「ライト センターSTT大会(1月末)」を開催して います。
…神奈川県は他の都道府県に比し競技人口が 多く幅広い年齢層の方が競技されており、県 内の各地域で定期的な練習が活発に行われて います。

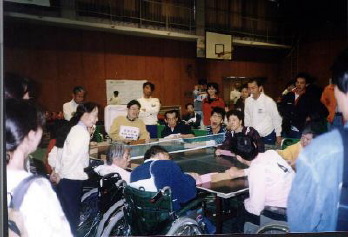
バレーボールをヒントにして卓球台でピンポン球を使って行う、障害の区別なく誰でもが楽しめるスポーツとして、京都市右京区の鳴滝養護学校で考案されました。
前校長の片山美代子教諭(現在知的障害者施設若草寮にご在職中)が鳴滝養護学校へ在職中に、重度障害者でも楽しめる競技をと学校の授業を中心に熱心にご指導され、京都障害者スポーツ振興会のご協力もあり、今では京都府全域に競技が普及しました。
現在は年間に三度程度で全京都の大会が行われ、毎回多くの参加者が集まります。
また、府下の各地域でも大会が行われるようになりました。

6人1チームの12人で卓球台を囲み、長さ30センチ、幅10センチ、厚さ1センチ程度の木製のラケットを各自が持ち、鉛入りの盲人卓球用のピン球を使用して、バレーボールの要領で必ず3打以内で相手コートに返して得点を競います。
ただし、ピン球はネットの下を通過させることとします。
ラケットは必ず木製で、一枚の板状で縦横30センチ以内の範囲であれば形状は問いません。
ただし、表面は平面でなければいけません。
1チーム6人のうちネット際の2人を
ブロッカーと呼び、主に攻守の要となります。
ブロッカー以外の4人はバックと呼び、主にレシーブやトスを行います。
サーブもこの4人が順番に行い、相手チームと交互にサーブを行います。
コートの外へピン球が落ちたり、3打以内で相手コートに返せなかった時、 ファウルをした時などに得点となります。

1. 競技ルールはバレーボールに準拠したものとなっています。
2. サーブブロック=ブロッカーは相手のサーブを直接打ち返すことは出来ません。
3. ドリブル=ピン球をラケットで二度打ちすると反則になります。
4. ホールディング=ピン球をラケットで押え込みながら打つなどして、打球音がしない時や不自然に打球の角度が変わった時は反則となります。
必ずはじき返すようにピン球を打ち返さなくてはいけません。
障害程度によりドリブル、ホールディングの基準は、ゲーム開始前に行う申し合わせ事項の確認の際に主審が判断を下すことになっています。
5. ネットタッチ=ラケットや手で、ネットやネットの支柱にふれると反則になります。
6. ボディーボール=ラケット以外の腕や身体でピン球を打つことは出来ません。
7. サポート=ネットの支柱にボールが当たった時は当てた側の反則となります。
8. スタンディング=椅子から腰を浮かせた時はその場で反則となります。
9. オーバーネット=ラケットがネットを越えて相手コートに入ると反則です。
10 ボールアウト=打球がネットを越えて相手コートに入った時、また、ネットの下を通って行ったピン球が相手コート上に落ちることなくコートの外へ出た場合は、 その打球を打った側の反則となります。
もちろん通常の打球がコート外へ出た時には打った側の得点になります。